
フェーズフリーアワード2023シンポジウムは2部構成で開催され、第1部では「フェーズフリーとデザイン 日常時と非常時の連続性」について、第2部では「フェーズフリーと社会、今後の展望」についてさまざまな意見や気づきの共有がおこなわれました。

司会進行を務めた武田ファシリテーター
今回のシンポジウムは事前アンケートの回答をもとにテーマが設定されたもので、ファシリテーターを務めたのはフリーアナウンサーの武田真一さんです。
第1部に登壇したのは主にデザインを専門とする審査委員で、フェーズフリーを世の中に浸透させるために「日常時と非日常の連続性をフェーズフリーなデザインとしてどのように提案していけるのか」が議論されました。
第2部に登場したのは実行委員長および社会貢献やイノベーションが専門の委員で、「フェーズフリーの製品やサービスを社会にどう普及させていくことができるか」「社会の仕組みそのものをフェーズフリーにできないか」をテーマに意見が交わされました。
第1部「フェーズフリーとデザイン 日常時と非常時の連続性」
冒頭の「フェーズフリーアワード2023で印象に残った応募対象、あるいはフェーズフリーに共感できる要素は」との質問に、最も熱量の高い反応を示したのは根津委員です。「出てきたものを見て、"なるほど、これがフェーズフリーか"とアップデートされた感覚。日常時と非常時への意識が変わり、みんなで広めていけば本当に社会が良くなると思った」と答えていました。
「ハードなプロダクトの提案からソフトの提案へ」との課題を感じたという原田委員は、「竣工したら建築物の完成、ではなくメンテナンスし続ける都市建築をやってみると面白いし災害に強くなるのでは」とコメント。
楽しみながら関わり続けることの重要性が示されると、根津委員の「変化を受容しつつ工夫して付き合い続けることが愛着を生む」との共感や、姜委員の「今ここを良くしようという考え方がもしもを良くすることにつながる」との意見など、日常時と非常時の連続性に触れる発言が続きました。

デザインが専門の玉井審査委員

デザインが専門の根津審査委員

建築設計が専門の原田審査委員

暮らしと食が専門の姜審査委員
次に示されたのは「デザインでどう日常時と非常時をつなげるのか」「フェーズフリーを形にする上で何を大事にすべきか」との問いかけです。
根津委員は、特別功労賞を受賞したコクヨのオフィス家具の例を挙げ「非常時に派手に変化したほうがいいという社内の声に対して、まずは日常時を良くするものを提案すべきとの姿勢を貫いた」点を評価。あらためて日常への価値提案の重要性を強調しました。
第1部を締めくくったのは、姜委員の「モンダミンのように、身近にあるものの中からフェーズフリーなものを見出すことが新たな気づきの連鎖につながる」との発言でした。
第2部「フェーズフリーと社会、今後の展望」
第2部ではまず「フェーズフリーの製品やサービスを社会にどう普及させていくか」が問われました。
阪本委員は、政策の実践例として鳴門市の『道の駅くるくるなると』に言及。「ふだんからみんなで利用しておいて災害時は拠点として使える、自治体が災害に備えるために必要不可欠な施設」と紹介しました。
武田さんは「このようなアイデアで社会が満たされるのを、果たして我々は待てるのか」と、フェーズフリーな社会が実現できていないことへの危機感を表明。
岩田実行委員長は「企業の取り組みが本格化すれば、フェーズフリーをものづくりの中心に据えることが当たり前になる社会がすぐ来るのでは」との期待を示しました。
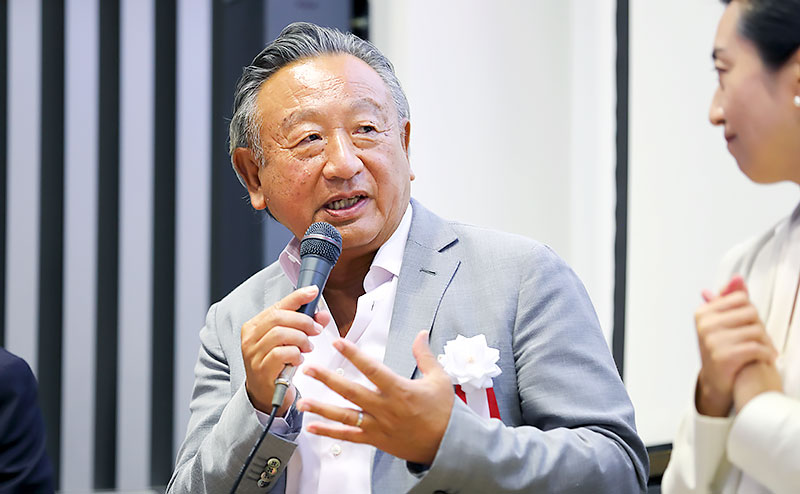
マーケティングが専門の岩田実行委員長
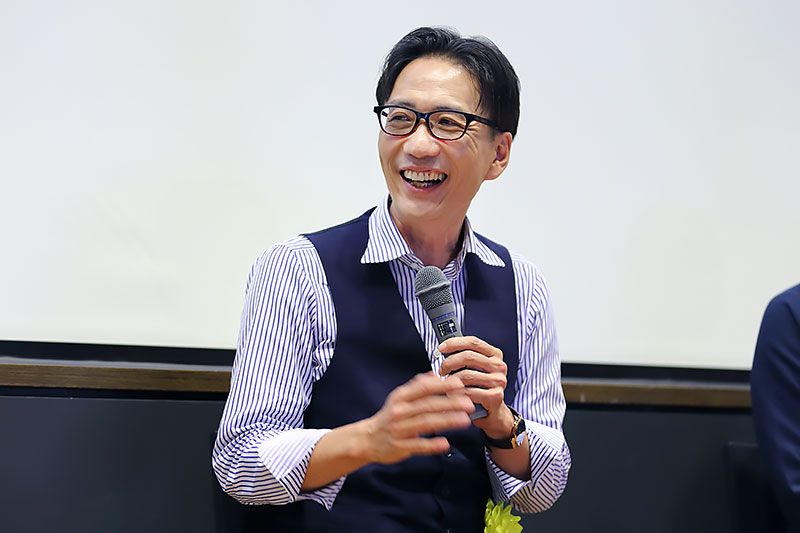
社会活動が専門の湯浅審査委員
「ふだんから売れている商品が非常時も役に立てば経済的な価値も社会的な価値も同時に得られる」とビジネスとして参加しやすい点をアピールしたのは佐藤委員です。
武田さんの「これまでのメディアや自治体による取り組みでは、企業の経済活動や人々の欲求に訴えて防災の施策を進める発想になじみがない」との指摘に、阪本委員は「防災にとらわれすぎず、日頃使っているもので非常時にもやっていける環境を作ろうという発想の転換が必要」と反応。
「あるものの掛け算で何を作っていくかが問題。ユビキタスなOSとして社会構造の変化を促しアップグレードできるデザインでなければ、普及しても"誰も取り残さない"という結果は出せない」と指摘したのは堀委員でした。

社会貢献が専門の堀審査委員

オープンイノベーションが専門の須崎審査委員
「フェーズフリーをどのように実装すれば"誰も取り残さない"社会になるのか」との問いに、湯浅委員は「結局は隣近所などふだんのつながりが大事」と回答し、「コミュニティやつながりはフェーズフリーと親和性が高い」と賛同したのは須﨑委員でした。
武田さんが「アワードのアイデアには楽しみながら社会を良くする、そしてみんなが経済的にも潤うというワクワク感があった」と初参加の感想を披露。「日々の暮らしの中ではなかなか気づかない、例えばつながりやコミュニティなどの価値が防災を支えている。みんながそういった事を考えられる余白のある社会こそ災害に強いのでは」との阪本委員の総括でシンポジウムは終了しました。

防災教育が専門の坂本審査委員

フェーズフリー協会の佐藤唯行
シンポジウムを振り返って
委員たちは応募者によるフェーズフリーへの理解の深まりに手応えを感じていたようです。ただ、佐藤委員から「フェーズフリーをデザインするときは非常時に向けた解決策の提示になりがちだが、日常への提案がないとフェーズフリーではない」との指摘もあり、デザインについては今後に向けた期待が大きいと思われます。
また、身近な人やモノとの関係性を示す語句が数多く登場し、日常時からそれらの関係性を向上させることが非常時の豊かさにつながる、との見解があらためて示されました。
玉井委員が「利用者の心に寄り添うデザインを」と述べたように、身の回りの関係性をより心地よく安心できるものにすることこそ、今後のフェーズフリーを考えるポイントかもしれません。
身近の範囲を広げる試みとして、岩田委員長が挙げた「東京の人が地方にセカンドハウスを持つ」という例は興味深いものでした。「もしもの時の避難先確保だけでなくふだんのつながりづくりの意味もある」と考えると、「今ある資源を再分配しながら再構築する、日本中を再デザインするチャンス」との発言が現実味を帯びてきます。フェーズフリーな社会の実現に向けて希望が見えたシンポジウムでした。

ディスカッションを楽しむ客席の方々
この記事をシェア












